
黒田 久一
惣菜のわかるオヤジのブログでは、フルックスグループ代表の黒田久一が、日々の出来事を発信いたします。


2010.06.26
今回、台湾に来た目的の一つ、サツマイモを見たかったので、いろいろと視察しました。
品種は「台農5号」と言うらしいです。
焼き芋にしたり(上)、蜜漬けしたり(中、下)して、食べます。
表皮は「コガネセンガン」に近いです。
特徴としては、ベチャ芋ですが、かなり甘い芋です。
もう少し、研究してみます。
黒田久一



2010.06.26
今回の出張も、ほぼ終了し、午後から、東京の大学生の長男が台北にやって来て、合流しました。
プライベート旅行です。
大学生になる長男や次男は、海外、特に東アジアは、是非体感してもらいたいです。
東アジアのコテコテの街に行ってもへっちゃらなように…。
先日、次男と話をしていて「お父さん、俺って地域密着型やから(笑)」と訳の分からない事を抜かすので(笑)、「アホか、お前は。地域密着型って、どういうこっちゃ」と。
この前、ガイヤの夜明けで、若者に対するインタビューで、全く同じ受け答えをする“草食系男子”を見るにつけ「若者よ、海外を目指せ!」と言いたいです。
夕方、鼎泰豊(ティンタアフォン)と言う小籠包では、最も有名店に行きました。
北京にも支店がありました。
もしかしたら世界各国に支店があるのかもしれません。
“本物”は、本当に美味しかったです。
現地の醤油やお酢も抜群ですが、中国方面に行くとき、私は、いつも持参する“秘密兵器”「味ぽん」は、本当に優れ物です(笑)。
黒田久一
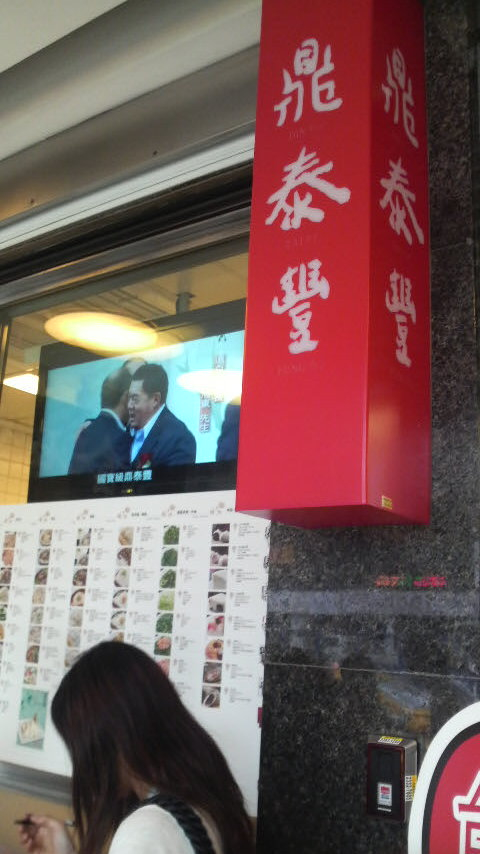


2010.06.25
昨日から台湾の第2の都市、高雄に来ています。
高雄の知り合いの台湾人の方に会う為です。
この方とは、2年前に一緒に、ある冷凍野菜の可能性を求めて、インドネシアに行った事があります。
Yさんは、中国に11もの会社を経営し、タイにも会社を持ち、グァテマラにも投資しています。
まさしくこれぞ「華僑」と言う典型的な台湾人です。
今日は、丸一日を掛けて、台南県や嘉義県の冷凍野菜(及び冷凍果実)工場に連れて行って頂きました。
私は、大学を出て新卒で入社した会社は、イトーヨーカドーグループのデニーズと言う会社です。
入社して一年間は、キッチンに立ち、コックをやっていました。
27年前の話です。
その頃のハンバーグやステーキのガロニ(付け合わせ)は、ほうれん草やインゲン豆のバターソテーでした。
それらの冷凍野菜は、100%、台湾産でした。
ブロック凍結した「凍菜(とうさい)」でした。
私は、八百屋(青果仲卸)の息子ですので、初めて「冷凍野菜」と言うモノに触れ、あまりにも大量にレストランで使用していたので「加工・業務用野菜」のあり方を目の当たりにしました。
当時、野菜の「冷凍モノ」に対しては、中央市場の業界人は、大半が馬鹿にしていたと思います。
どちからと言えば“邪道”みたいな。
それ以降、現在に至るまで、物凄い勢いで「加工・業務用の世界」に、冷凍や塩蔵された野菜が多用されました。
その後、台湾の農産物の優位性は、長く続かず、程なくして、生産地は、中国に移りました。
弊社も約10年前に安徽省や山東省、江蘇省などにシフトしました。
しかしながら、ここ数年、中国産の不祥事(餃子事件)などにより「チャイナフリー」が求められたりし、その中国の優位性も揺るぎ始めました。
そして私自身は、中国の国力の増大により、日本の立場(購買力)そのものも揺るぎ始めました。
タイ、ベトナム、インドネシア、台湾、韓国など日本は、中国以外の東アジアの諸外国からも「原料」を調達しています。
今、中国を見直そうとする動きは、当然ではありますが、しかしながら、やはり総合的に判断(インフラ、ボリューム、管理面など)してみて、まだ中国の優位性は、まだあるように、今回の台湾視察を通じて再認識もしました。
商品群などにより、その判断は別れるかとも思いますが…。
そして、それを理解した上で、国内産地の重要性も再認識も致しました。
写真は、
(上)高雄港
(中)たっぷりのフカヒレスープ
(下)台湾を代表する凍菜の枝豆とほうれん草です。
明日は、再び、台北に戻ります。
長男が、成田からやって参りますので、合流します。(プライベート旅行で)
黒田久一


