
黒田 久一
惣菜のわかるオヤジのブログでは、フルックスグループ代表の黒田久一が、日々の出来事を発信いたします。


2011.10.17
こちらもベルギーが発祥の世界的企業です。
スーパーマーケットです。
DELHAIZE
です。
日本語での発音が難しいようで、デルヘーズとか、デレーズとか、マスコミによってバラバラです。
http://www.delhaize.be/portal/_fr/index.aspx?Lang=fr
アメリカにも、相当に昔から進出し、その地位も半端じゃありません。
以前、ノートにメモしているデータでは、デレーズ・アメリカは、SM部門で堂々の第5位。
まさしくグローバル企業です。
ル・パン・コティディアンといい、凄いですね。
ベルギーは、人口は、わずか1000万人で、世界第77位の小国です。
店内で目に留まったのが、カロリーコントロールしたお惣菜とプライベートブランドのオーガニックのお菓子です。
DELHAIZEのプライベートブランドは、オーガニックが中心みたいでした、
黒田久一



2011.10.17
今日は、フランクフルトとブリュッセルを往復しました。
片道3時間。
今やユーロ圏内は、当たり前ですが、隣の国に行くのに、パスポートコントロールもありません。
通貨も統一されていますので、隣国へ行くと言う感覚ではありません。
昔とは様変わりしました。
ユーロ統一は、現時点では、問題も多く、前途多難です。
しかしながら、ヒトやモノの行き来が、これ程までに自由になったメリットも当然あります。
この便利さの後戻りは、戦争でも起こらない限り、絶対にないなと感じました。
さて、ブリュッセルからフランクフルトへ戻る道中の事です。
座席が、対面シートでした。
たまたま乗り合わせた向かいの人は、タイ人。
その隣は、インド人でした。
真隣りは、ドイツ人の女性でした。
ドイツ人女性以外のアジア人全員(私も含む)が、列車が動き出すと、iPadを出しました(笑)。
ドイツ人の女性が、どいつもこいつも?(シャレです)(笑)、アジア人は、せわしなく、iPadしやがって、と言うような?目付きを感じました。
それにしても、日本語とタイ語と英語の文字を同時に、iPadで見たのは初めてです。
これが、今の世の中を象徴してるのかもしれません。
どんな民族も瞬時にどこからでも、情報を得ている…。
商売が厳しくなるのは、当然だと痛感します。
つまり瞬時に価格情報など全てがオープンになる時代です。
益々、知恵をひねり出さないと生き残れませんね。
黒田久一

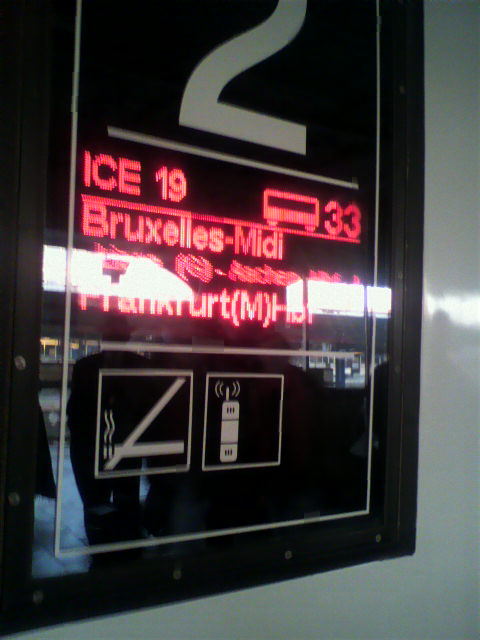
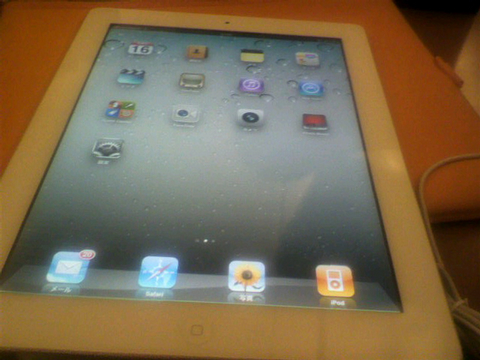
2011.10.17
GroBmarkthalle
グロブマルクトハレ
ドイツ語で、卸売市場の意味らしい?です。
グロブが、英語のホールセール、マルクトは、マーケット、ハレがホールかと、勝手に想像しています。
本日、早朝より、フランクフルトの卸売市場に行って来ました。
フランクフルト中央駅からタクシーで行きましたが、私は、ドイツ語が全く分からないので、事前に“GroBmarkthalle”と書いたメモをタクシードライバーに手渡して、行きました。
車中では、片言英語でドライバーと会話しましたが、アラブ系らしい運ちゃんで、相手も片言英語でした(笑)。
事前に調べてた卸売市場の場所は、街の中心でしたが、2004年に郊外に移ってました。
以前の場所は、ドライバーいわく、バンクCITYと言うので、多分、金融街に変わっているのだと思います。
フランクフルトの卸売市場も、他のヨーロッパ市場と同様に、入場ゲートでは、パーミッションのカードが必要でしたが、タクシードライバーは、適宜、ガードマンと対応してくれて、何とか入場する事が出来ました。
卸売市場に入った瞬間に肌で感じる空気は、ロンドンの卸売市場と同じように、やはり、活気が全く感じられませんでした。
大変残念ですが…。
ちょうど一年前も万代さんの欧州視察団に参加し、今回同様に延泊し、ロンドンのニュースピタルフィールド市場に参りました。
その時は、農水省の方(ジェトロに出向中)に案内してもらいました。
ドイツの卸売市場も、イギリス同様に、大手小売業の寡占化が、相当に進んでいますので、大手企業は、自前のセンターを保有しているでしょうから、卸売市場の機能は、低下していると思われます。
フランスのランジス市場のように、巨大化し、ハブ市場(集荷市場)としての位置を確保した市場は、それなりの生き方があるのでしょうが、その他の卸売市場は、大変だと想像します。
ロンドンの市場業者の生き残り方は、もはや、大手量販店相手のホールセーラー(卸売業者:仲卸)ではなく、ディストリビューター(外食向け小分け卸)としての生き方でした。
今、閑散とする市場内を歩いて、カメラを撮っていたら、イラついたような男性から、怒鳴られました。
私は、同じ市場人なので、バカげた態度で撮影せず、遠慮がちに撮ってましたが…。
市場業者は、青果だけで、70~80社だと思います。
構造的には、プラットホームとフルフラット(地べた)との段違いの組み合わせの建物で、ランジス同様に、積み込みはしやすいです。
A棟とB棟に別れていて、A棟は、仲卸店舗、B棟はその倉庫群となっていました(一番下の写真)。
市場の中で、ピッキングされた荷物を見る限り、単独店のSM向けか、レストランなどの外食向けかと感じます。
全ての時間帯をいた訳ではないので、実態はわかりません。
私は、いろんな国々に行く度に、卸売市場は、必ず、立ち寄るようにしています。
今回もいろんな事が頭をよぎりました。
弊社グループが「惣菜のわかる八百屋」を志向しようと思うに至ったのは、世界的なこのような傾向を以前より、肌で感じ、また、食品小売業が、益々、中食シフトする事がきっかけでした。
つまり、単純な青果仲卸への危機感が、大きな決断に至るきっかけでした。
青果物に手を加える、つまり青果加工へのシフトは、世界的な流れでもあります。
青果物をホール(丸のまま)で、消費される時代は、終わりました。
これからも、青果物は、多様な姿で、流通し、そして消費されて行くと思います。
今回のアヌーガメッセ(展示会)も、昨年のシアル(パリ)でも、強く感じましたが、世界的に中食へシフトしているのは事実です。
より安全&安心で、より簡便に、ノンクックで、美味しいものを…。
一年ぶりのヨーロッパでしたが、スーパーマーケットの店頭商品は、さらに、中食化しています。
弊社グループのスローガンであります「惣菜のわかる八百屋」の実現は、まだまだ、道半ばであり、問題も山積しています。
ものづくり現場力も、これからです。
しかしながら、少しずつでも、前進して参りたいと思います。
早朝のフランクフルトの卸売市場のカフェにて
黒田久一


